
患者さんが熱発していたからクーリングしたら、先輩に怒られちゃった・・・

発熱時にクーリングしていいかは、タイミングによって決まるよ。
看護師歴7年、急性期病棟に勤めてきた私が、発熱時の看護ケアについて分かりやすく解説するよ!
今日のポイント
- クーリングするのは…
手指があたたかい、患者さんが「暑い」と言っているとき、体温が40℃以上のとき
- クーリングしない(むしろ保温する)のは…
末梢冷感やシバリングがある、患者さんが「寒い」と言っているとき

根拠を理解して看護を実践できれば、きっと看護が楽しくなっていくよ!
発熱の機序:体温はセットポイントに合わせて上下する
発熱の機序には主に2種類あります。
- 気温が高いなどの外環境により、体温調節が追いつかず発熱する=熱中症
- セットポイントが上昇し、発熱する
セットポイントとは
セットポイントとは、体内の設定温度のことです。
脳の視床下部に体温調節中枢があり、ここでセットポイントが設定されます。

セットポイントが上がれば体温も上がり、セットポイントが下がれば体温も下がる仕組みになっています。
セットポイントが上がる原因

セットポイントが上がるのは、細菌やウイルスといった病原体が体内に侵入したときです。
セットポイントを上げ、体温を上げることで、細菌やウイルスの力を弱めたり、免疫力を高めたりして、病原体と闘う体内環境を作り出します。
発熱は、病原体に対する防御反応なのです。
腫瘍熱という、がん患者さんが毎晩発熱する現象があります。これは、悪性腫瘍を病原体と誤認し、セットポイントが上がることで起こる発熱です。
体温が上がるまで体に起こること
セットポイントが上昇したら、自動的に体温が上がるわけではありません。
体温を上げるには体が頑張る必要があります。設定温度を上げられた暖房のごとく、体力を使って体温を上げるのです。

このとき体内では、次のようなことが起こっています。
- 骨格筋を収縮し熱産生→シバリング
- 末梢血管を収縮し熱放散抑制→末梢冷感
- 体温とセットポイントの差で相対的に「寒く」感じる→悪寒

私も熱の出始めにこんな症状が出るな~。
体温が下がるまで体に起こること
炎症が改善すると、セットポイントが下がります。
すると今度は、設定温度を下げられた冷房のごとく、体温を下げるように体が頑張ります。

- 骨格筋収縮を抑制し熱産生抑制→倦怠感
- 末梢血管を拡張し熱放散→発汗、手指があたたかくなる、頭痛
- 体温とセットポイントの差で相対的に「暑く」感じる
こういったことが体内で起こります。
発熱の看護:体温が「上がり切るまで」と「上がり切ってから」で行うべき看護ケアが変わる
発熱時の看護ケアは、以下のように2パターンに分けて考えます。
- セットポイントが上がってから、体温が上がり切るまで→体温を上げるのを手伝う
- セットポイントまで体温が上がり切ってから→体温を下げるのを手伝う
体温が上がり切るまでの看護
体温が上がり切るまでに患者さんに起こっていることは先程説明した通り、
- 骨格筋を収縮し熱産生→シバリング
- 末梢血管を収縮し熱放散抑制→末梢冷感
- 体温とセットポイントの差で相対的に「寒く」感じる→悪寒
です。つまり症状として、シバリング、末梢冷感、悪寒がみられるときは、上がったセットポイントに向けて一生懸命体温を上げている段階です。
セットポイントまで体温を上げればシバリングは止まりますから、体温を上げるお手伝いをしましょう。
つまり、保温します。
保温の方法

- 室温を上げる
- 衣服や掛け物を増やす
- 電気毛布を使う
患者さんは「寒い」ので、その訴えに合わせた対応をすればいいのです。

この時点で「熱が上がると大変!」とクーリングを始める看護師さんを何度か見たことがありますが、これは間違いです!
セットポイントまで体温が上がり切らない限り、体は体温を上げようと頑張り続けて、シバリングは止まらないからです。
体温が上がり切ってからの看護
体温が上がり切ってから患者さんに起こっていることは、これも先程説明した通り、
- 骨格筋収縮を抑制し熱産生抑制→倦怠感
- 末梢血管を拡張し熱放散→発汗、手指があたたかくなる、頭痛
- 体温とセットポイントの差で相対的に「暑く」感じる
でした。このうち体温が上がり切ったと確実に分かるサインは、手指があたたかい、「暑い」と訴えていることです。(倦怠感や頭痛は他の機序でも起こり得るので、これだけでは体温が上がり切ったと言い難いです。)
こういったサインが見られたら、今度は体温を下げるお手伝いをしましょう。
つまり、クーリング、解熱剤の投与をします。
クーリング
クーリングの方法

- 衣服や掛け物の調整
- 室温を下げる
- 氷枕やアイスノンを頸部、腋窩、鼠径部に当てる
患者さんは「暑い」ので、その訴えに合わせて涼しくします。
氷枕やアイスノンは、太い血管が皮膚表面近くを通っている部位(頸部、腋窩、鼠径部)に当てて冷やします。血液を冷やすことで体温を下げることができるのです。
さらに、クーリングには体温を下げる以外に、患者さんが爽快感を得る目的もあります。
爽快感を得やすい部位は頭部です。クーリングにはあまり効果的ではないから間違い!と言われがちですが、患者さんが気持ちいいと感じていれば立派な看護ケアです。


体温が42℃を超えるなど早急な解熱が必要なときは、頸部、腋窩、鼠径部の3点クーリングが適しているね。
解熱剤の投与
主に解熱剤として投与されるのは、アセトアミノフェンとNSAIDsです。
解熱剤の種類
- アセトアミノフェン(アセリオ、カロナール、アンヒバetc)→脳の体温中枢に作用してセットポイントを下げる
代表的な副作用:肝機能障害
- NSAIDs(ロピオン、ロキソニン、ジクロフェナクetc)→炎症のもととなるプロスタグランジン生成を抑制する
代表的な副作用:消化性潰瘍、腎機能障害
副作用が少ないので、初回はアセトアミノフェンを投与することが多い印象です。
いずれの薬剤も、解熱する過程で末梢血管を拡張し発汗を促します。そのため、以下に注意します。
①血圧低下に注意する
投与前に血圧測定し、普段より低めなら医師に相談してから投与しましょう。
②清潔ケアを行う
患者さんが楽になってきた段階で、更衣や清拭といった清潔ケアを検討しましょう。

ただでさえ体力を失っている状態かつ、病原体と闘う体力を必要としている状態ですので、シャワー浴は控えた方が無難です。
参考:体温は下げるべきなのか

せっかく体温が上がって免疫力が高まったのに、すぐに体温を下げていいの?

そんな疑問を持てるナスちゃんは、ここまでの内容をよく理解できているね。
でも体温が上がったままだと、以下のようなデメリットがあるんだ。
①体力が奪われ、逆に抵抗力が落ちてしまう
自分が発熱しているときを思い出してください。だるくて、水分をとるので精一杯、ごはんは食べる気にならないし、なんだか頭も痛い・・。この状況が続けば、脱水や栄養不足になるし、病原体と闘うための体力がどんどん奪われていってしまいます。
②脳の神経細胞がダメージを受ける
体温が42℃を超えた状態が続くと、体内のタンパク質も変性してしまう可能性があります。特にデリケートな脳の神経細胞から損傷され、重大な後遺症を残すことがあります。

だから、体温が上がり切ったら体温を下げる必要があります。
まとめ
- クーリングするのは…
手指があたたかい、患者さんが「暑い」と言っているとき、体温が40℃以上のとき(42℃を超えるおそれがあるため)
- クーリングしない(むしろ保温する)のは…
末梢冷感やシバリングがある、患者さんが「寒い」と言っているとき

今日は発熱時の看護ケアについて解説したよ!

発熱のメカニズムから理解できたから、明日から自信を持って看護できそうだよ!

よかったら読者登録して次回記事も見てね。
みんなが少しでも楽しく看護できるように、これからも応援しているよ!
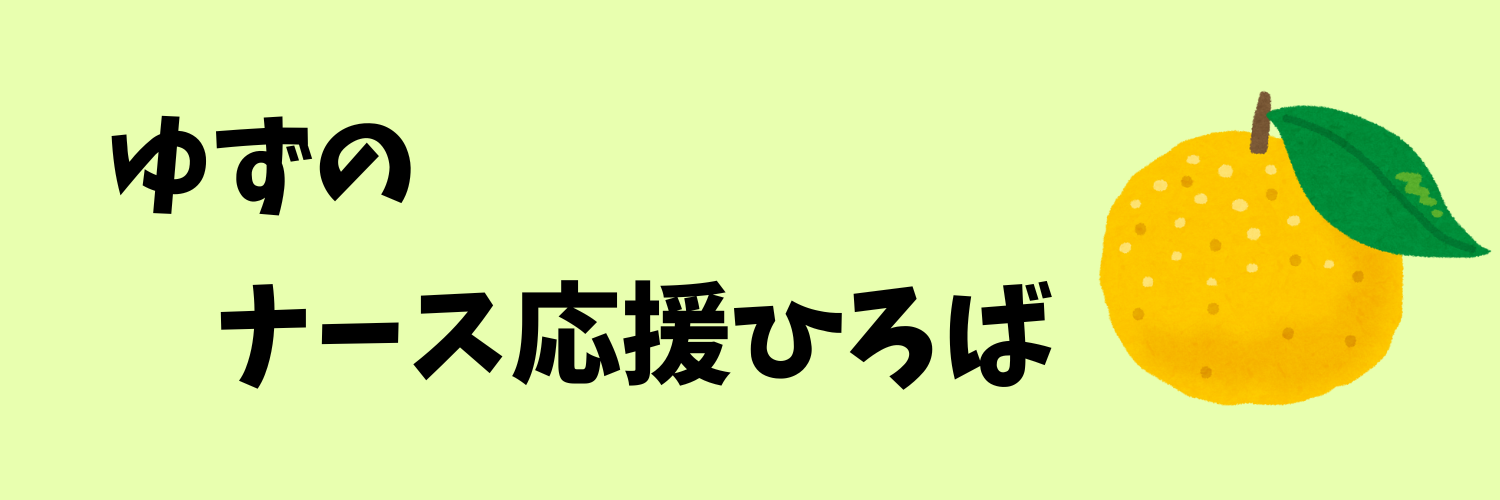


コメント