
まだ痰培とってないの?もう遅いじゃん、インシデント書いて

え、す、すみません・・またインシデントだ・・

培養検査は間違えやすいポイントがあるんだよね。
でも大丈夫!看護師歴7年、急性期病棟に勤めてきた私が分かりやすく解説するよ!
今日のポイント
培養検査の2カ条
①抗生剤投与前に実施しよう!
②コンタミネーションを防ごう!

これを読めば培養検査に関するインシデントは予防できるよ!
一緒に学んでいこう!
培養検査とは:検体内の菌を調べる検査
培養検査は感染症が疑われるときに実施される検査です。
血液培養(血培)、痰培養(痰培)、尿培養(尿培)、便培養などがあります。

正確には、一般細菌検査の一部が培養検査ですが、医師や看護師の間では一般細菌検査のことを「培養」と呼ぶことが多いです。
検体の中に菌がいるか、どんな種類の菌か、を調べることで、適切な治療(抗生剤など)を選択できます。
培養検査を開始して1日目に、菌の大きな分類や、菌によっては具体的な菌種を推定できます。
実際に菌種が同定できるのは、3-7日後となります。

でも培養検査の結果が出る前に、抗生剤投与をすることがあるよね?

その通り。
でも、菌種が特定できた3-7日後から抗生剤を投与するのでは、全身に菌がまわって敗血症になってしまい、手遅れになってしまいます。
そのため、どの部位が感染しているか(肺炎なのか、尿路感染症なのかなど)、経過等から当たりをつけて抗生剤を選択し、できるだけ早期から投与し始めるよ。

培養検査の結果が出たら、抗生剤を変更するかそのままでいいかを医師が判断します。
培養検査を実施するタイミング:抗生剤投与前に実施しよう
培養検査がオーダーされるまでの流れ
培養検査を実施するのは、感染症が疑われるときです。
実際の流れ
①患者さんに発熱等の症状が出る
②採血でCRP高値、WBC(白血球、ワイセと呼ばれる)高値など、感染症が疑われる検査結果が出る
③培養検査と抗生剤のオーダーが出る
抗生剤投与前に培養検査を実施する理由

抗生剤(抗菌薬)は、体内の細菌を殺す作用をもつ薬剤です。
抗生剤を投与して体内から細菌が少なくなってから、培養検査を実施(検体採取)するとどうなるでしょうか。
本当はいたはずの細菌が検体内に採取できず、正しい結果が出ない可能性があるのです。

培養検査の注意点:コンタミネーションと感染を予防する
コンタミネーションを予防する
これまでお話しした通り、培養検査は検体内の細菌を調べる検査です。
つまり検体内に、患者の体内に存在しなかった細菌が混入しては絶対にいけません!
この「患者の体内に存在しなかった細菌が混入してしまうこと」をコンタミネーションといいます。
コンタミネーションを防ぐため、培養検査は基本的に無菌操作で行います。
それぞれの検査でのコンタミネーションを防ぐ手順を解説します。
血液培養検査

2セット採取する
検査結果で検出された菌がコンタミネーションかを判断するために、違う血管から2セット採取します。
下肢やカテーテルから血液を採取しない
下肢やカテーテルからの血液採取は、コンタミネーションが多くなってしまうので、できるだけ上腕で採取します。ただしカテーテル感染を疑う場合は、カテーテルから血液を採取することがあります。
採血部位の消毒は、アルコール綿に加えて、0.5%以上のクロルヘキシジンアルコールまたは10%ポビドンヨードを使用する
まずアルコール綿で皮膚表面を広く消毒後、0.5%以上のクロルヘキシジンアルコールまたは10%ポビドンヨードで消毒します。これによって皮膚常在菌を死滅することができます。
ボトルのゴム栓をアルコール綿で消毒する
ボトルゴム栓の表面は無菌ではないので、消毒が必要です。
痰培養
唾液ではなく痰を採取する
唾液には多くの常在菌が含まれるため、できるだけ痰を採取します。

基準としてMiller&Jones分類があるよ。
膿性痰と唾液混入の度合いを肉眼的に観察し、採取した喀痰が検査に適しているか評価するためのスケール。
| 分類 | 喀痰の肉眼的性状 |
|---|---|
| M1 | 唾液、完全な粘液痰 |
| M2 | 粘液痰の中に少量の膿性痰を含む |
| P1 | 膿性部分が1/3以下 |
| P2 | 膿性部分が1/3~2/3 |
| P3 | 膿性部分が2/3以上 |
Miller&Jones分類のP1、P2、P3が高率に原因菌が検出される、つまり適切に検査できるとされます。
尿培養検査
中間尿またはカテーテル尿を滅菌容器に採取する
出始めの尿は尿道口付近に付着した常在菌が混入しやすいため、中間尿を採取します。

膀胱留置カテーテル挿入中であれば、採尿ポートをアルコール綿で消毒して、滅菌シリンジで採尿します。
おむつ内失禁の患者であれば、導尿して採尿します。このとき導尿カテーテルが滅菌容器に付着しないように注意します。
便培養検査
清潔に洗って乾燥させたポータブル便器または滅菌済み容器に排便する
水洗トイレを使用する場合は、滅菌済み容器に排便したものを、検体スピッツに採取します。水道水が混入してしまうと、塩素によって菌が死滅する危険性があります。
感染予防をする
全ての患者の検体採取において、血液、体液、分泌物、排泄物、健常でない皮膚、粘膜は感染性があるものとして対応し、標準予防策を実施します。
培養検査を実施する患者は、感染症が疑われる患者ですので、特に注意が必要です。
次の感染症・病原体が疑われる場合、感染経路別予防策を加えます。(感染症は一部例です。)
接触予防策
黄色ブドウ球菌(MRSA)、腸球菌(VRE)、ESBL産生菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、ロタウイルスやノロウイルスなどによる感染性胃腸炎、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、単純ヘルペスウイルス、疥癬、流行性角結膜炎、アデノウイルスなど
飛沫予防策
インフルエンザウイルス、インフルエンザ菌(小児)、A群溶連菌、ムンプスウイルス、風疹ウイルス、マイコプラズマ、レジオネラ、アデノウイルス、百日咳、髄膜炎菌、新型コロナウイルスなど
空気予防策
結核、麻疹、水痘、播種性帯状疱疹
まとめ

今日は培養検査実施時の注意点について解説したよ!

急な指示で慌てちゃったけど、患者さんの治療を決める大事な検査なんだね。
確実に検査できるようにしなくちゃ!

よかったら読者登録して次回記事も楽しみにしてね。
みんなが少しでも楽しく看護できるように、これからも応援しているよ!
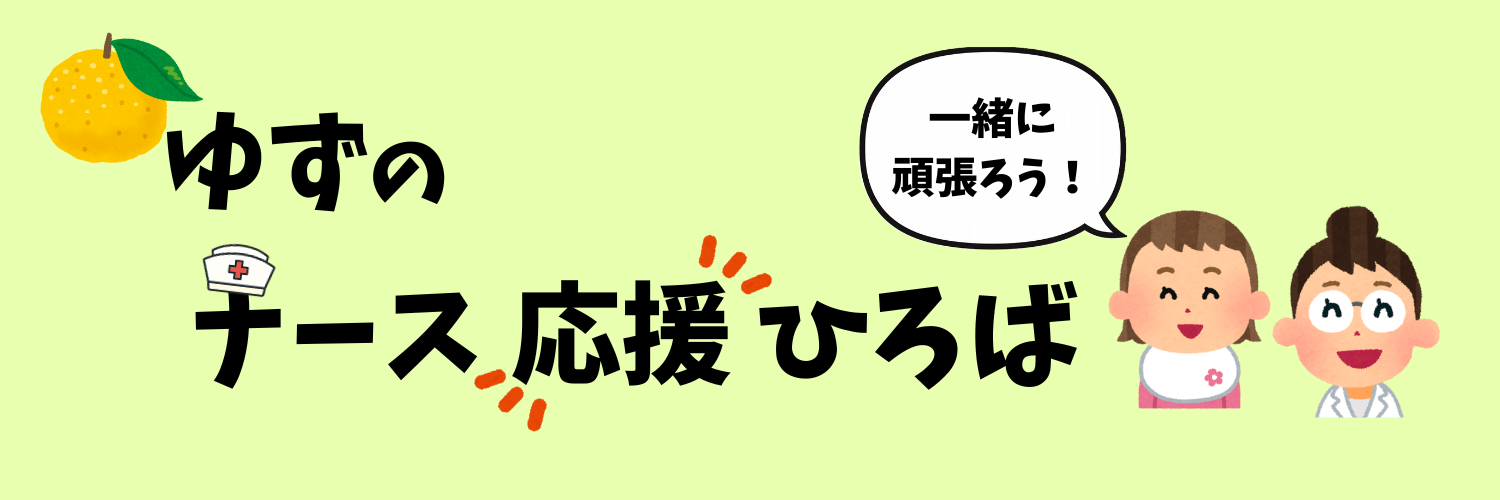



コメント