
SpO2は99%あるから問題なしっと。

ナスちゃんちょっと待って~!
その患者さん、本当にそのSPO2で大丈夫かな?

この患者さんは体内の酸素量を増やすために酸素投与しているんだから、
SPO2は高ければ高いほどいいんじゃないの?

実はそうとは言えないパターンがあるんだ。
今日は、SPO299%でも安心しちゃいけないパターンを4つ紹介するよ!
これを知って正しく患者さんのアセスメントができるようになると、看護がどんどん楽しくなっていくよ!
ぜひ最後まで読んでね。
今日のポイント
貧血、Ⅱ型呼吸不全の酸素投与、循環不全のときは、SpO299%で安心しない!

それぞれについて解説していくよ。
前提:SpO₂とは?
SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)とは、体内のヘモグロビンのうち、酸素と結合しているヘモグロビン(=酸化ヘモグロビン)の割合(%)を指します。

えーと・・・それってどういうこと?
空気中の酸素は呼吸によって肺胞まで運ばれます。
肺胞で、血液中の酸素と結合していないヘモグロビン(=還元ヘモグロビン)と酸素が出会うと、酸素がヘモグロビンと結合し、酸化ヘモグロビンとなります。
この酸化ヘモグロビンを多く含む血液(=動脈血)は、全身へと酸素を運びます。

全身の細胞では、エネルギーを作るために酸素が使われ、ヘモグロビンは酸素を離して還元ヘモグロビンに戻ります。
その血液(=静脈血)は心臓、肺へ戻り、再び酸素と結合します。

SpO2は、皮膚を通して末梢の動脈血中にどのくらい酸化ヘモグロビンがあるか(酸素と結合している割合)を測定した値です。

正常では、ヘモグロビンの約96~99%が酸素と結合しています。これがSpO2の「正常値」とされます。
SpO2が高いほど:ヘモグロビンが酸素をしっかり運んでおり、全身に酸素が届いている状態。
SpO2が低いほど:ヘモグロビンが酸素をあまり運べず、全身の酸素が不足している状態。
ですが――
実はこの「数値が高い=安心」「低い=危険」という考え方が当てはまらない場合があるのです。
これが今回のテーマです。
本題:SpO₂が99%なのに危険な状態4選
① 貧血
SpO2が99%なら、ほとんどのヘモグロビンに酸素が結合しているということなので、数値上問題なさそうに見えます。
しかし、この患者さんが貧血だったらどうでしょうか。
貧血とは、赤血球もしくはヘモグロビンが不足した状態です。
そもそもヘモグロビンの量が少ないので、運ばれている酸素の量も少ないのです。
つまり、細胞では酸素不足が起こります。必要なエネルギーを生成できず、易疲労感やめまいといった貧血症状が現れます。

じゃあ貧血が改善するまでどうしたらいいの?
重度貧血の場合、SpO2に異常が無くても酸素投与を行うことがあります。できるだけ多くのヘモグロビンに酸素が結合してくれることを期待するためです。
貧血のために酸素投与をする場合、SpO2100%でも投与を中止しません。主治医に、酸素投与の目的と指示を確認しておきましょう。
また、エネルギー消費量を減らすことで、酸素消費量も減らすことができますので、安静が重要な治療となります。
② 酸素投与中のCO₂ナルコーシス
CO2ナルコーシスとは
CO2ナルコーシスとは、体内に二酸化炭素(CO2)が過剰に蓄積し、意識障害などの中枢神経症状が出現する病態をいいます。

酸素が足りてるかばかり見ていたけど、二酸化炭素が多すぎてもよくないんだね。

その通り。
なぜ二酸化炭素が体内にたまってしまうのか、詳しく見ていこう。
キーワードは「呼吸中枢」と「Ⅱ型呼吸不全」だよ。
呼吸中枢とは
私たちの呼吸は、脳幹(延髄)にある呼吸中枢によってコントロールされています。
呼吸中枢は血液中の酸素(PaO2)や二酸化炭素(PaCO2)の量を感知し、呼吸の深さや速さを調整しています。
たとえば・・・
- PaO2が低い(酸素不足)→ 酸素を取り込むために換気量を増やす
- PaO2が高い(酸素多い)→ 換気量を減らす
- PaCO2が高い(二酸化炭素多い)→ CO2を排出するために換気量を増やす
ここで問題になるのが、Ⅱ型呼吸不全の患者さんです。
Ⅱ型呼吸不全とは
Ⅱ型呼吸不全とは、PaO2≦60Torr かつ PaCO2>45Torrの状態を指します。
つまり、酸素不足(低酸素血症)なうえに、二酸化炭素が過剰(高CO2血症)になっている状態です。
代表的な疾患はCOPDや、気管支喘息の重症例などです。
なぜCO2ナルコーシスが起きるのか
Ⅱ型呼吸不全の患者さんでは、二酸化炭素が過剰な状態に慣れてしまい、呼吸中枢がPaCO2の変化に反応しにくくなります。
そのため、PaO2の上下のみを感知して換気をコントロールするようになります。
ここで酸素を投与すると、PaO2が上昇し、呼吸中枢は「もう酸素足りてる」と判断。
その結果、呼吸が抑制され、換気量が減少します。
換気量が減少すれば、息を十分に吐き出せなくなり、体内にCO2がさらに蓄積。
こうしてCO2ナルコーシスに陥ってしまうのです。

Ⅱ型呼吸不全の患者さんに酸素療法をするときに、CO2ナルコーシスに気をつければいいんだね。
具体的には、どんなことに注意すればいいの?
CO2ナルコーシスを防ぐための注意点
①不要な高流量酸素投与を避ける
Ⅱ型呼吸不全の患者さんに必要以上の酸素投与を行うことで、呼吸抑制を引き起こしCO2ナルコーシスに至ります。
ガイドラインでは、COPD急性増悪時の酸素療法のターゲットSpO2を88~92%に維持するよう推奨しています。
医師の指示を確認し、必要に応じて酸素微量計などを使用し、この範囲を超えないように調整します。
また、ベンチュリ―マスクを使って酸素濃度を一定に保つこともあります。
②CO2ナルコーシスの兆候を観察する
- 酸素投与開始前後の呼吸数・リズム・深さの変化

換気量が減っていると、呼吸抑制が起こり始めているサイン。
でも、初期のCO2ナルコーシスでは呼吸促迫が起こることもある。
呼吸数が多くても、呼吸が浅いときは注意が必要だから、呼吸の深さもしっかり観察してね。
- 頻脈
- 発汗
- 頭痛
さらに進行すると…
- 意識レベルの低下(傾眠~昏睡)

リスクのある患者さんに上記の症状が出ていたら、すぐに医師へ報告・相談しよう。
③ 循環不全(ショックなど)
パルスオキシメーターは、末梢血管のヘモグロビンをみています。
そもそもこの末梢血管の血流が悪ければ、SpO2を正確に測ることはできません。不安定な値が表示されます。

じゃあどうしたらいいの?
パルスオキシメーターでSpO2値を測定するときは、その部位の循環状態を観察します。
- 末梢冷感がないか
- 皮膚の色(青い、青白い)
- その部位より中枢で圧迫されていないか
循環が悪いときは、マッサージや加温で血流が改善されることがあります。
また、別の部位(手指、足趾、耳たぶ、額等)で安定して測定できることがあります。
どこでも測定できない場合は、呼吸状態を観察した上で、SaO2(動脈血酸素飽和度)を調べることがあります。
SaO2は動脈血ガス分析をする必要があるので、患者さんの苦痛は大きいです。

SpO2は呼吸状態を観察する値の一つに過ぎないよ。SpO2が上手く測れないなら、呼吸数、呼吸のリズム・深さ、呼吸音の左右差・雑音の有無、努力呼吸の有無等から総合的にアセスメントする必要があるよ。
④ 一酸化炭素中毒(CO中毒)

病棟で発症することはほぼないけど、知っておこう。
一酸化炭素(CO)中毒とは、火災現場や、室内で換気不良のままストーブを使い続けるといったことが原因で起きます。
COはヘモグロビンと強く結合してしまいますが、パルスオキシメーターはそれをO2と結合していると誤認してしまいます。
結果、SpO₂が99%でも実際は重度の酸素欠乏となっています。
- 重度の酸素欠乏にも関わらずチアノーゼは起こらない
- 頭痛や吐き気、意識障害が起こる
まとめ:SpO₂は“ヒント”、答えは患者にある

SpO₂は、体の中で起きていることを知るための「ヒント」にすぎないってこと、分かってもらえたかな?

SpO2が高いから大丈夫ってわけじゃないっていうことがよくわかったよ!
貧血や、COPDの酸素投与では特に注意ってことだね!

今日の内容は少し難しかったかもしれないけど、臨床でそういった患者さんをみて理解を深めていけば大丈夫!
今後も看護のコツを発信していくから、よかったら読者登録、Xのフォローをして次の更新を待っててね。
参考文献:

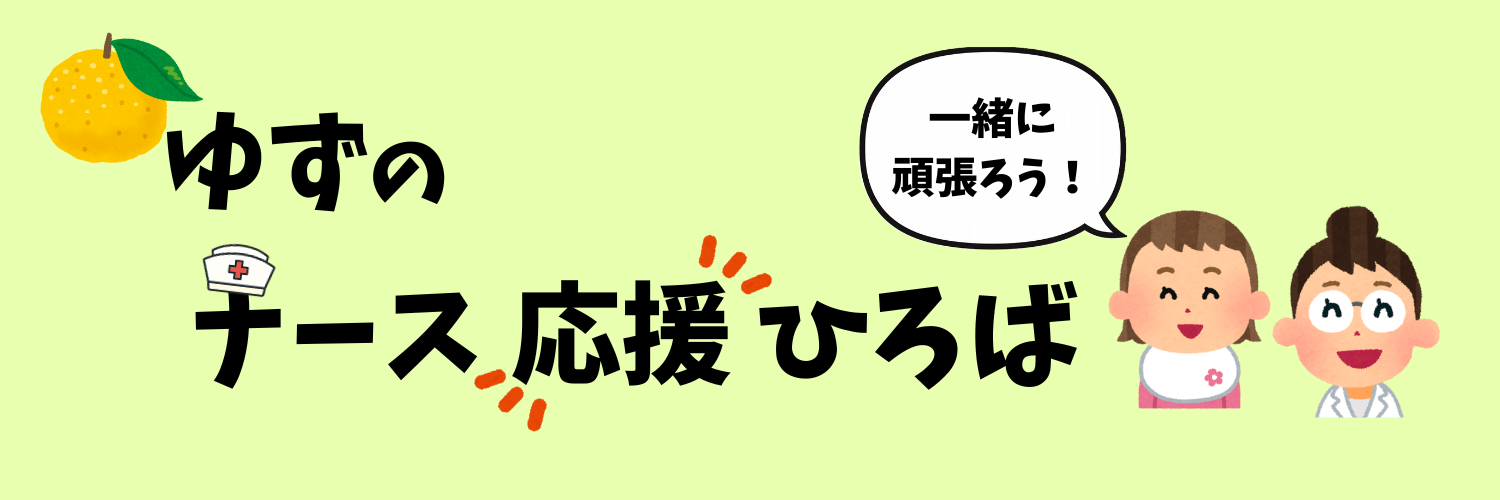



コメント