こんにちは、ゆずです!
今回は、転倒後の頭部外傷について解説していきます!

転倒して頭を打ってしまうとどうなっちゃうのかな。

転倒後に死亡する事例のほとんどが頭部外傷によるものです。
また、後遺症を残すこともあります。

転倒で亡くなってしまうことがあるんだ・・

そうなの。
だから、転倒しても頭を打たないようにする予防策、転倒した後の観察項目を確認しておこう!
転倒時の頭部外傷を予防するには、衝撃リスクを抑える!
頭部外傷って?
転倒で起こる頭部外傷により、次のような病態となり得ます。

急性硬膜下血腫
- 硬膜下に出血した状態
- 片側にできることが多いが、両側のこともある
- 出血が多く脳を圧迫すると、神経症状や頭蓋内圧亢進症状がみられる
- 強い頭痛を伴う
- 頭部を打った直後~数時間後に症状が出現する
- 迅速な手術での血腫除去により救命できることがある
外傷性くも膜下出血
- 外傷性SAH(ザー)ともいう
- くも膜下腔に出血した状態
- 頭部を打った直後から頭痛、嘔吐、意識障害がみられる
脳挫傷
- 脳組織の損傷や出血
- 前頭葉、側頭葉に生じやすい
- 頭痛・嘔吐に加えて、損傷した部位が対応する神経症状が出現する
例:片麻痺、失語、けいれん、意識障害など - 損傷した脳組織は回復しない
- 脳浮腫を予防する薬物療法が行われることが多い
これらは、いずれも頭部CTで発見できる検査です。
頭を打ったか分からない場合は、そのように報告しましょう。頭部CTをすぐに行うことが推奨されます。
転倒・転落後の頭部打撲はここを観察しよう!
頭部外傷の場合、受傷直後は普通に話ができたが、その後急速に症状が悪化し死に至ることがあります。
転倒直後だけでなく、転倒後は継続的に以下を観察し、記録するようにしましょう。
どのくらいの間隔で観察、記録するかは、施設によって決まっている場合が多いです。
🧠神経学的所見
- 意識障害、健忘
- 頭痛
- 片麻痺、失語、けいれん発作
- 瞳孔不同(アニソコリア)
🧠頭蓋内圧亢進症状
- 血圧上昇、脈圧増大
- 徐脈
- 呼吸抑制(呼吸数減少、呼吸リズム不整)
頭部外傷のリスクが高い患者

次のような患者さんは、頭部外傷や重症化リスクが高いです。
抗凝固薬・抗血小板薬内服中
抗凝固薬・抗血小板薬内服中で易出血傾向となっている場合、頭蓋内出血のリスクが高いです。
急激に頭蓋内病変が進行する場合があります。
ベッド柵を乗り越える転落
転倒転落で頭部外傷となるのは、床に頭部を打ちつけた場合が多いです。
ベッド柵を乗り越えて転落した場合、非常に高い位置から床に頭を打ち付けてしまうことになるので、頭部外傷のリスクは極めて高いです。
頭部外傷を起こさない、障害を軽くするための予防策

なんだか不安になってきたよ・・

患者さんの自由を守りながら、頭部外傷になるような転倒を予防するにはどうしたらいいか、一緒に考えてみよう。
衝撃吸収マット
ベッド周りの床に衝撃吸収マットを敷くことで、頭を床に打ちつけた場合の衝撃を和らげることができ、頭部外傷のリスクを軽減します。
ただし、衝撃吸収マットの厚みのために段差が生じ、歩行時につまずいたり、点滴スタンドが引っかかると逆に転倒のリスクにつながることがあります。

夜寝ている間だけ使用することもあるよ。
低床ベッド
ベッドを低床にしておくことで、衝撃吸収マットと同様に、床に頭を打ちつけた場合の衝撃を和らげることができ、頭部外傷のリスクを軽減できます。
ただし、立ち上がることが可能な患者さんの場合、ベッドが低すぎると立ち上がるのが困難になり、ベッドに戻るときには逆にバランスを崩して危険な可能性もあります。
歩行時には、ベッドの高さを立ち上がりやすい高さ(足裏が床にしっかり接地するぎりぎりの高さ)に調整する必要があります。
4点柵か3点柵か
4点柵は動きの少ない患者さんの転倒転落を予防できますが、動ける患者さんは逆に柵を乗り越えることになり、床に頭部を打ちつけた場合の衝撃が強まるため、頭部外傷のリスクを上げてしまいます。
また4点柵は抑制に該当するという考え方から、3点柵を使用する場合があります。
以下のような場合は4点柵が適している可能性が高いです。
<4点柵が適している場合>
- 患者に柵を乗り越える能力がない
- 不随意運動により身体が大きく動く
- ギャッチアップ時に座位姿勢が崩れて横に倒れる
以下のような場合は4点柵がかえって危険になり得ます。
<4点柵が適さない場合>
- 認知機能低下・せん妄がある
- 患者に柵を乗り越える能力がある
- 柵を自分で外してしまう可能性がある
このような場合では3点柵を使用したり、L字柵の使用を検討します。
ベッド周囲の環境整備
ベッド柵を乗り越える能力のある患者さんの場合は特に、床頭台の上の私物やポータブル
トイレ、車いすなどの患者が触れたり動きたくなる離床の誘因をベッド周りに置かないようにし、適切なタイミングで患者の行動をサポートするような配慮をすることが望まれます。

逆にすぐに使うものは手元に置いておく工夫が必要だね。

ティッシュペーパーとか、携帯電話、お水とかかな?
あとナースコールもだね!
まとめ
転倒時の頭部外傷を予防するには、衝撃リスクを抑える!

患者さんの転倒は防ぎたいものだけど、患者さんの自立や自由を考えると、絶対に防げるものではないよね。
“転倒による二次障害”を防ぐために、適切なケアを行っていこう!
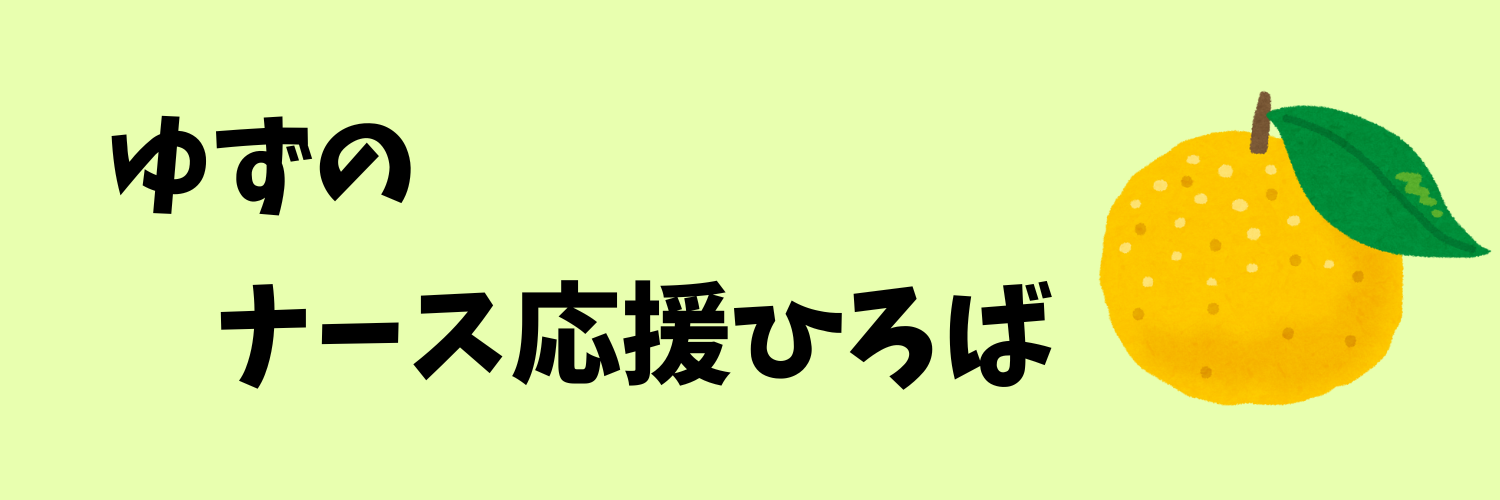



コメント