
まだ痰培とってないの?もう遅いじゃん、インシデント書いて

え、す、すみません・・
またインシデントだ・・

ナスちゃーん!どうしたの!

痰培養の検査とるの遅くなって怒られちゃった・・

なるほどね!それは遅くなったんじゃなくて、順番を間違えただけかも!
また悲しい思いしないように、一緒に学んでいこうね!
今日のポイント
培養検査は抗生剤投与前に実施せよ!

え、それだけ?

本当にそれだけ!
理由を解説するね。
培養検査って何?
培養検査は感染症が疑われるときに実施される検査です。
正確には、一般細菌検査の一部が培養検査ですが、一般細菌検査のことを培養検査と呼ぶことが多いです。
血液培養(血培)、痰培養(痰培)、尿培養(尿培)、便培養などがあります。
検体の中に菌がいるか、どんな種類の菌か、を調べることで、適切な治療(抗生剤)を選択できます。
培養検査を開始して1日目に、菌の大きな分類や、菌によっては具体的な菌種を推定できます。
実際に菌種が同定できるのは、3-7日後となります。
菌種が特定できた3-7日後から抗生剤を投与するのでは、全身に菌がまわって敗血症になってしまい、手遅れです。
そのため、どの部位が感染しているか(肺炎なのか、尿路感染症なのかなど)、経過などから当たりをつけて抗生剤を選択し、できるだけ早期から投与し始めます。
培養検査をする前に抗生剤を投与してはいけない理由
抗生剤(抗菌薬)は、体内の細菌を殺す作用をもつ薬剤です。
つまり、抗生剤を投与して、上手くいけば細菌が少なくなった体内から検体をとっても、培養検査の結果が正しく出ないことがあるのです。
こんなシンプルな話なのに、なぜみんな間違ってしまうのか、一緒に考えてみましょう。
ちなみに、検体を採取するのが抗生剤投与前であれば、検体の提出は抗生剤投与後でも問題ありません。
なぜ抗生剤を投与してから培養検査を行ってしまうのか
①抗生剤のことをよく知っているから
抗生剤は、できるだけ早く投与することで敗血症の予防になります。
感染症の治療は、この敗血症を予防することが最も重要で、患者さんの予後に最も関わります。
このことを知っていると、「早く抗生剤を投与しなきゃ!」と焦ってしまうかもしれません。

敗血症については、次回詳しく解説するよ。
②指示時間が指定されないから
できるだけ早く抗生剤の投与を開始するために、初回抗生剤投与の投与時間は指定されないことも多いです。培養検査についても同様です。
そして、抗生剤と培養検査がセットでオーダーされることが多いですので、看護師がカルテを見たときにはまず目についた抗生剤から準備してしまうということがあります。

電子カルテで、抗生剤投与前に培養検査を実施するようにアラートが出るといったシステムがあればいいかもしれないですね。
③培養検査の指示が出るのは緊急時だから
患者さんが発熱したとき、採血結果で感染を示す値(CRP上昇、WBC上昇)がみられたときに、培養検査を行うことが多いです。
予測が難しい状況なので、突然オーダーが入って慌てるのは当然です。
まとめ
今日伝えたいことは、
培養検査は抗生剤投与前に実施せよ!
本当にこれだけです。
でもここまで読んでくださったみなさんは、その場に立った自分を想像してくれたと思います。そして、その場面が来たとき、ハッと思い出せるはずです。

急な指示で慌てちゃったけど、
気を付けて確認するようにしようっと!

そう考えられることが素晴らしい!
間違いは誰にでもある。
患者さんと自分を守るために、
これからも看護のコツを知っていこう。
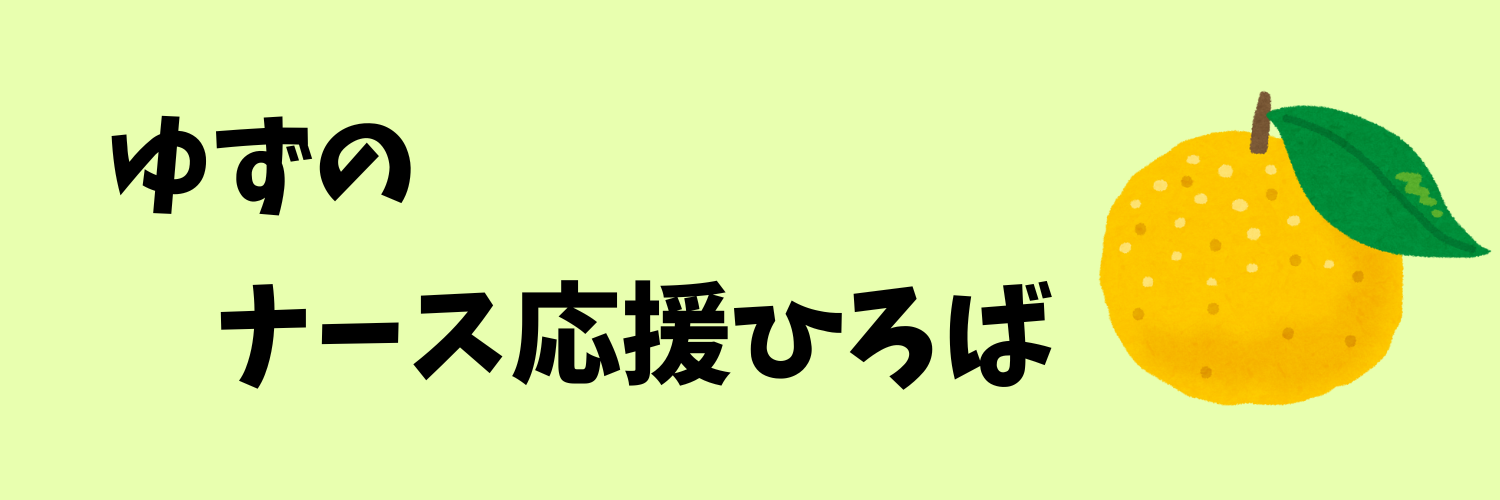



コメント